その胸の痛み、もしかしたら「冠微小循環障害」かもしれません。
「胸が痛い」「胸が締め付けられるような不快感がある」「息苦しい」。
「もしかして狭心症?」と心配して大きな病院で心臓の検査を受けたが「特に異常ありません」と言われてホッとしたのに症状は続く。そんな経験、ありませんか?もしそうならその原因は「冠微小循環障害」かもしれません。
冠微小循環障害とは?
冠微小循環障害は心臓の表面を走行し、心臓に血液や酸素を供給する太い血管である冠動脈ではなく、その冠動脈から無数に生える非常に小さな血管(冠微小血管)の攣縮や構造的な異常で心臓に充分な血液が流れなくなり、胸の痛みや締め付けられるような不快感を引き起こす病気です。表面的な検査をしただけでは診断を見逃されることがあり、「ストレス」などで片付けられてしまうことが少なくありません。冠微小循環障害は循環器内科専門医でも疑わないと診断が難しい疾患です。
なぜ「異常なし」と言われるのか?冠微小循環障害のメガニズムと診断の難しさ
胸が痛いというと多くの内科医師や循環器内科医師は冠動脈CT検査や冠動脈造影検査で「目に見える血管の狭窄」を探します。しかし冠微小循環障害は目に見えない細い血管の異常であるためこれらの検査では診断できず「異常なし」、と診断されてしまうことが多くります。
微小循環障害の原因はいくつかありますが、代表的なものをあげます。
-
冠微小血管の異常な収縮
寒冷刺激やストレス、喫煙などで冠微小血管が強い収縮を引き起こし心臓への血流が流れにくくなります。 -
血管の内皮機能障害
血管の内側にある内皮細胞は一酸化窒素を酸性することにより、血管の拡張を促します。しかしこの機能が何らかの原因で低下することにより十分な拡張が得られず、血流が低下します。 -
冠微小血管の構造的な変化
高血圧や糖尿病により冠微小血管に動脈硬化を引き起こし、血流が低下します。
冠微小循環障害は治療しなくても良いのか?
冠微小循環障害は放置すべきではありません。胸痛のため生活の質(QOL)が低下、繰り返す症状に対してカテーテル検査などを繰り返す時間的、経済的損失や予後への悪影響を引き起こします。女性に多く見られ、更年期の症状と誤解されることもあります。
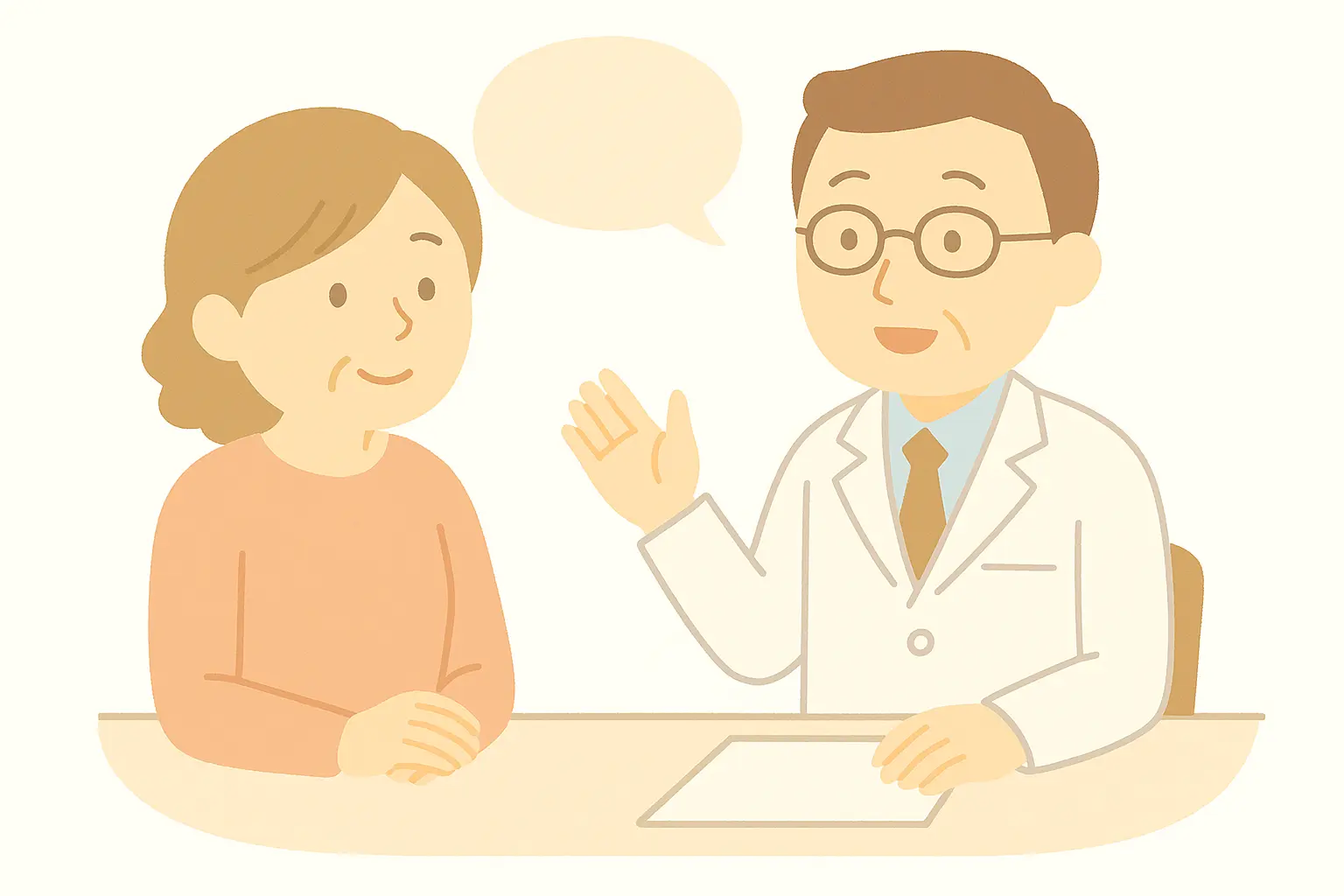
冠微小循環障害の診断は?
冠攣縮誘発テスト(アセチルコリンまたはエルゴノビン負荷試験)
心臓カテーテル検査でアセチルコリンという薬剤を心臓の血管に注入して、血管が過度に収縮(攣縮)するかどうかを判定します。この試験で、目にみえる冠動脈の攣縮が認められなくとも心電図で心臓に酸素が足りない変化と普段悩まされている胸痛が出現すれば、冠微小循環障害(厳密にはその中で冠微小血管攣縮という病態)と診断できます。
冠微小血管拡張能の検査
目に見えない冠動脈の拡張能を検査します。冠動脈に特殊なワイヤーを挿入し、
冠血流予備能(CFR)
冠微小血管抵抗指標(IMR)
という二つの指標を測定し、診断します。
こちらの検査が必要と判断した場合、連携している近隣の病院へと紹介いたします。
治療は?
治療には薬物療法と薬物療法があります。
有酸素運動(ジョギングや水泳、早歩きなど)を心拍数が100-120/分程度の運動を1回20-30分程度、週3回以上を目安としておこうことが勧められています。ただし、運動を始めてから胸痛が出現するようなら強度や時間は短めから始めましょう。
薬物療法は心臓の血管を広げるカルシウム拮抗薬や硝酸薬での治療が基本となります。
また喫煙は攣縮を誘発することが知られているため、喫煙しているのであれば必ず禁煙しましょう。自分一人での禁煙が難しければ、当院の禁煙外来までご相談ください。
「原因不明の胸痛」に悩む患者様へ
「他院で問題ないと言われた…」、「どうして胸痛があるのわからなくて不安だ…」という悩みを抱えていませんか?あなたの胸の痛みは決して「気のせい」ではありません。当院では微小循環障害の診断、治療に力を入れています。冠微小血管拡張能や冠攣縮誘発検査はやや特殊な検査でありますが、私が過去に勤務しおりました川崎幸病院(リンク:https://saiwaihp.jp/)でこの検査を受けられます。当院からスムーズに紹介させていただきますので、悩んでいる方はご相談ください。